不安症(パニック症や社会不安障害など)を悩む人におすすめの書籍をまとめました。
不安症の人はすでにとても頑張っている人が多い印象です。
なぜなら、この不快な感覚から逃れたい一心で、本を読んだり・医者に頼ったり・漢方を試したり・ヨガを始めたり・瞑想を始めたり・運動をはじめたり・整体に通ったり・・・。いわゆる「治るためにはこれをしたらいいよ」と言われたことをすべて実践しているからです。
あなたは充分に頑張っています。あなたはそのままでいいのです。
私は不安症が治ったわけではありません。ですが、闇雲に何かにトライすることは辞めました。いろいろ読んだり、試したりしましたが、結論「受容する」ことが一番いいのではないかと思ったからです。
今回は、その考えに至った大切な書籍3冊をご紹介いたします。(2022/9/13 1冊追加)
12年苦しんだ不安症を完全完治させた方法(著者:Sorato)
実際に克服した人の体験記に勝るものはありません。核心にふれる部分は、本の真ん中くらいから始まりますが、読んでない方は是非。
Kindle Unlimited 会員は、無料で読むことができます。
私はとても参考になり、この本の紹介で、3番目に紹介する「不安のメカニズム」を読むことになります。
不安を乗り越える10のステップ(著者:ベヴ・エイズベット)
著者自身もパニック障害経験者。
オーストラリアの人気マンガ家であり、作家、およびカウンセラー。
自身の経験から、訓練を受けたカウンセラーとして不安神経症で悩む人たちに、カウンセリングや講演、ワークショップも行っている。
不安を乗り越える10のステップ 巻末作者プロフィール
イラストと短文で書かれており、非常に読みやすい本でした。
私がブログで紹介している本をすべて読んだ後に出会いました。「不安症を受け入れる」という考えを先に知った上で読んだせいか、内容に対する引き込まれ具合が一番強かったです。(そしてなんといっても一瞬で読める!けど心がじわっとあつくなります)
不安を「あいつ」と形容し、「あいつってどういう時にでてくるの?」など、「あいつ」にまつわる10のセクションで物語は進んでいきます。
自分を怖がらせることばかり言っているのだから、「どうしてわたしなの?」ではなく「こうなるのは当然かも」と思うほうが理にかなっているかも。という考え方は、本当にそうだなと感じました。
以下、心に残った文章を抜粋で紹介していきます。
5.自分を癒す
自分のことを、かつて小さな子どもだったころの自分として考える。あなたはただ愛されたかっただけ・・・あなたは小さかったんだから・・・傷つきやすかったし・・・信頼していた・・・あなたはできるだけのことをやった・・・そして、彼らに喜んでもらおうとした。
でも、あなたはじゅんぶんに愛してもらえなかったかもしれない・・・傷ついたかもしれない・・・無視されたかもしれない・・・あまりにも多くのルールがったかもしれない・・・それともなさすぎたかも・・・
あなたは自分の気持ちを表現することができなかったかも・・・罰を受けることを恐れて・・・それとも、あなたは小さかったので、ただ誤解していただけなのかもしれない。
・・・それはあなたのでいじゃない。自分のことを許してあげる。(わたしは小さな子どもだったんだわ!)
自分が小さかったころに受け取れなかった愛を自分に与えよう。そして・・・「あいつ」と仲直りしよう・・・「あいつ」はあなたの中にいる小さな子どもにすぎないのだ・
不安を乗り越える10のステップ STEP7 こわれた「あいつ」を修理する p105
要するに、他の人があなたについてどんな意見をもっていたとしても・・・あなたは彼らの言うことを信じていたのだ!でもあなたは異議を唱えることができるのだ!もし・・・あなたが自分のすべての面を受け入れ、自分が自分でいることを申し訳ないと思うのをやめたら・・・異議を唱えることができる。自分の応援団、ディレクター、カウンセラー、そして友達でいよう。「ごますり病」を捨ててしまおう。(彼らが認めてくれなかったとしても、それが何だっていうの?)失敗けっこう。(OK・・・失敗しちゃったけど、次はもっとうまくやるわ!)彼らの言うとおりだと証明することをやめること!でも、だれかにひどく傷つけられたらどうする?それでも、あなたは選ぶことができる・・・傷ついたままでいて・・・過去にあなたをずっと傷つけさせるか・・・それとも、過去の出来事が現在のあなたにもたらす影響力を断ち切るか・・・(もうおしまい!エネルギーを切ってやる!)←過去とかかれたコンセント口からコンセントを抜くイラスト
つまるところ、最高のリベンジはあなたが人生を楽しむこと!
不安を乗り越える10のステップ STEP8 「あいつ」や他の人との関係を修復する p122
不安のメカニズム(著者:クレア・ウィークス)
不安症は「不安神経症」とも言うらしいのですが、こちらの表現のほうが個人的にしっくりきます。
なぜなら、この「不安でたまらなくなる」「体に不快感を感じる」感覚は、私たちの神経が「過敏になりすぎている」から起こっている現象だからです。
この過敏になりすぎた「神経によるいたずら」によって、頭は不安でいっぱいになり、パニックのようになり、そして体の不快感を感じるようになります。それらの症状との向き合い方について、本著は解説してくれています。
参考になった部分
- 不安がおこるメカニズムを知る
- 症状を「受け入れる」
- 恐怖とは戦わず「浮かんで通り過ぎる」
- 最終的には「時間の流れに任せる」
不安がおこるメカニズムを知る
心と神経が極度に過敏化していると、感情ーとくに恐怖感ーに押しつぶされるように感じることがあります。しかも、苦しんでいる人の多くは、それが過敏化のせいだとは気付いていないため、そうした状態に戸惑い、恐怖を感じて、自分自身を「恐怖→アドレナリンの分泌→恐怖」という悪いサイクル(悪循環)に陥れてしまいます。ここが実は一番重要な「転換点」です。なぜなら、今まで単に過敏状態にあった人が、神経症へと移行するのはまさにこの瞬間だからです。
完全版 不安のメカニズム 第四章「感情の疲労」より
自分が感じる恐怖心や不快感が、どういった仕組みでおこるかを丁寧に解説してくれています。
「こういう仕組みで起きていたんだ」ということが分かると、安心感が得られます。また「どうすれば完治できるのか?」という問いの答えにもつながります。
私たちは無意識のうちに湧いてくる考え方のクセがあります(それをするとこんなことが起きる。自分には無理だ、など悪く考えるクセ)。「なぜ起きるのか」ということをしっかり理解することで、こういった「心のクセ」と冷静に向き合うことができるようになり、その結果、冷静に対応することもできるようになります。
「心のクセ」を知ることで、第2の不安(恐怖心の増殖)をおこさないことが大切です。
症状を「受け入れる」
神経が疲れ切って、頭も心が疲れ果てている人には確かに休養が必要です。
ですが、ある程度回復した人は「家の中に篭り続ける」はかえって症状の回復を妨げることがあるようです。そういった人は、パニックや不安感に正面から立ち向かい、それらと戦わず「受け入れる」ことが回復へのステップにつながります。
私たちは無意識に「またあのパニック感が襲ってきたらどうしよう」「またあの不快感を味わうのが怖い」と恐れ、症状と戦っています。
このように戦うのではなく「受け入れる」という姿勢がとても大切です。
受け入れるとは受容ともいいますが、「あの症状がきても良い」と思い、その症状が通りすぎるのを待つ状態です。体の不快感や感情をじっと観察するのではなく、新聞を読んでいるのなら読み続けることが大切です。ようはその症状が起きても「別にいいや」「あれが起きても大したことではない」と気にせず、日常の生活を過ごすことが大切です。
■恐怖そのものに向き合う
神経症は多くの場合、いろいろな症状や体験に対する恐怖が原因となって発症します。それを完全に治すには、まず恐怖そのものに向き合うことから始める必要があります。とくに、恐怖がピークに達している時に、「適切な方法で」向き合うことが大事です。
でも、なにも考えずにただ闇雲に恐怖に向き合おうとするのではダメです。確かにそうするのは勇敢なことではあるかもしれませんが、たいていは効果がなく、疲れ切ってしまうだけです。神経症から回復するためには、どうやって恐怖と向き合ったらいいか、適切な方法を学ぶ必要があります。それが、次からお話する三つの方法ー「受け入れる」「浮かんで通り過ぎる」「時が経つのにまかせる」という三つの方法です。
第十一章「真正面から向き合う」
恐怖とは戦わず「浮かんで通り過ぎる」
ここで「浮かんで通り過ぎる」を実践するとどうなるか、見てみましょう。麻痺状態に陥ってしまった人は、自分に無理やり何かをさせようとするのをやめて、身体からできるだけ力を抜き「肩や手足から力を抜き、全身がだらりとして、ふにゃふにゃになったような感覚を実際に感じるようにして)、大きく息を吸ってから、自分が何の抵抗も受けることなくふわふわと浮かんで前に進んでいるところを想像しながら、ゆっくりと息を吐くようにすると、緊張が少しとけて筋肉が緩み、前に進むことができるようになります。最初は手足が震えたり、ぎくしゃくとした足取りかもしれませんが、きっと前に進めます。
第十三章「浮かんで通り過ぎる」より
浮かんで通り過ぎたことで得られる効果については、次の通りです。不安感もある種「思い込みだ」と気づかされるエピソードです。
私が診てきた患者さんの中には、絶え間ない恐怖のために身も心も緊張し切って、歩くことも、腕を動かして口に食べ物を運ぶことも自分にはできない・・・と思い込むまでになってしまった患者さんもいました。そのような状態になっていたある男性は、もう何週間もベットに寝たきりでいました。少し話してみると、その麻痺状態の原因が筋肉の異常ではなく、頭の中の「思考」にあることが理解できる人だとわかりましつぁ。彼は、自分の行動を邪魔している思考の上を浮かんで通り過ぎることによって、筋肉を解放する方法を学びました。二、三日後、彼は誰の助けも借りずに、食べ物を自分の口まで「浮かばせて運ぶ」ことができるようになりました。そして、歩くこともできそうだと言い出したのです。
このことは、彼のいた病棟にちょっとした騒ぎを巻き起こしました。石、医学生、看護師たちが、彼の様子を見に集まってきました。この患者さんが立ち上がって歩こうとすると、足元のおぼつかないその姿を見た一人の看護師があわてて「気をつけて!倒れるわよ!」と叫びました。
後になって、患者さんはこの時のことを振り返ってこう言いました。「あの言葉はまるで予言のように聞こえました。もう少しで本当に床に崩れ落ちそうでした」でも、その時、頭の後ろで一つの声が聞こえたそうです。それは「浮かぶんだ。そうすればきっとできる。恐怖の上を浮かんで通るんだ!」と言う声でした。そして次に、彼の言葉によると「私は浮き上がり、病棟を一回りして帰ってきました。みんなもそうですが、私自身、本当にびっくりしました。
いま例として挙げた二人は、自分の思考によって自ら恐怖をかき立てていました。このような思考は疲れ切った頭にとてもしつこく付きまとい、強迫観念のようにこびりついてしまうことがあります。ですから、そういった思考を逃すための通路がある、つまり「浮かばせて、頭の外に出してやる」ための排気口のようなものがある・・と想像することが助けになる場合があります。例えばある女性は後頭部にそのような出口があると考えるようにしていました。また、別の女性は右の耳上(一昔前の商店の主人などが鉛筆をはさんでいた場所です)に出口があって、そこからそういった思いがふわふわと浮きながら流れ出るところを想像するようにしていました。また、そういった思いを小さなボールと考えて、そのボールが自分の頭の中からポンポン飛び出ていくところを想像するようにしていた女性もいました。
第十五章「いろいろな症状の治し方」
最終的には「時間の流れに任せる」
じっくりと神経症になったように、治るのにも時間が必要ということをまず理解してください。
回復のカギは「忘れること」ではありません。「もうそんなことはどうでもいい」と思えることが大事です。ですから時間の経過が必要なのです。
第十四症「時が経つのに任せる」
回復の過程でぶり返しがあり、「また自分は振り出しに戻った」「私はもう治らない」と自信を失う必要もありません。なぜならこういったぶり返しも、回復の過程で必ず必要だからです。
むしろそのぶり返しを恐れて、自信をなくすことの方がずっと深刻です。
しかし、無理をすると身体に負荷がかかるので、本当にゆっくりでいいのです。「まずはこれならできるかな」と思うところからで大丈夫です。外を散歩することが目標なら、まずは「靴を履いて家の前に出る」ことを目標としてもいいでしょう。それが大丈夫になったら「外を1分歩く→5分歩く→10分歩く」と徐々にステップアップしていけばいいのです。
自分で設定した階段が、辛く感じるのなら、その1段をさらに10段に細分化してもいいと思います。
できるスピードでいいのです。
時間がかかることですので、ゆっくりとやっていきましょう。
ですから、次のようなことをぜひ試してみてください。
・緊張や恐怖を感じても、その上を浮かんで通り過ぎる。
第十五章「いろいろな症状の治し方」
・マイナス思考や心無い言葉も、浮かんでやり過ごす。
・戦うのを止めて浮かんで通り過ぎる。
・何事も受け入れ、もっと多くの時間が経つのに任せる。


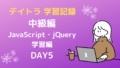
コメント